遺言、相続放棄、遺産・財産管理、売買・贈与・相続・抵当権抹消等の不動産登記、司法書士による監修などのご相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所
遺言相続,不動産登記が多い司法書士長田法務事務所の公式HP
東京都墨田区両国2-21-5-507の司法書士長田法務事務所内
営業時間:平日は午前10時~午後6時、土休日は事前予約制
墨田区,江東区,台東区,江戸川区,葛飾区,荒川区,足立区,北区の相続など
司法書士の無料相談もあります
お気軽にお問い合わせ下さい
03-3635-2119
遺産分割の方法とリスク-墨田区の司法書士長田法務事務所
墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。
税金の申告が必要な遺産分割はご自分の判断で行わずに、税理士や役所にもお問合せ下さい。
遺産分割と相続、相続不動産の売却などのご相談は、墨田区の司法書士長田法務事務所へ
税務申告の際は、税理士も紹介しています。
相続に関するご相談は、東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ
☎ 03-3635-2119
司法書士長田法務事務所の紹介へ
お客様の声へ
遺産分割の方法とリスクのもくじ
相続が始まったら、葬儀から49日までの故人を偲ぶ手続きに疲れてしまい、これから始まる遺産分割協議の方法や処分のリスク管理がおろそかになることがあります。ご注意下さい。
- 遺産分割は何回やり直してもいいの?
- 遺産分割の期限は気にしなくていいの?
- 遺産分割で負債(相続債務)の負担を決めればそのとおりになるの?
- 遺産が分割しにくいので、代償分割を検討したい
- 遺産が分割できないので、いっそ換価分割をしたい
- 相続人の一人が生きているか否か不明です。遺産分割できますか?
- 遺産分割協議書の不動産や預貯金の書き方がよくわかりません
相続不動産等の売却(アドバイザリー)サービスもあります。ご相談下さい。
もくじを見て遺産分割の方法とリスクにご興味がある方は、次からの本篇をご覧下さい。
相続(全般)へ
遺産分割についてへ戻る
遺産分割のありがちなリスクの本篇
相続手続きとは、原則として民法上の手続きですが、税法の知識も必要となります。
ここにあることは、普通にありがちな行為です。
司法書士や税理士のアドバイスを受ける事がリスクを回避するために必要です。
1.遺産分割は何回やり直してもいいの?
A.遺産分割は、民法上の回数制限はありませんが、気をつけましょう。
 遺産分割をやり直すことで税務署に贈与税の指摘を受けることがあります。
遺産分割をやり直すことで税務署に贈与税の指摘を受けることがあります。
適当な遺産分割は、かえって相続人間にトラブルを生むことになります。
2.遺産分割の期限は気にしなくていいの?
A.遺産分割協議自体には、原則として民法上の期限はありませんが、
具体的相続分に期間制限が設けられましたのでご注意を。
 ※ 民法904条の3新設(令和3年改正:令和5年4月1日から施行)
※ 民法904条の3新設(令和3年改正:令和5年4月1日から施行)
① 原則
相続開始から10年経過後の遺産分割については、特別受益及び寄与分の規定の適用はできなくなりました。
② 例外
A.相続開始から10年経過する前に相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき。
B.相続開始から10年の期間満了前6か月以内の間に遺産分割請求ができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅してから6カ月以内に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき。
➡ このやむを得ない事由は、仕事や海外旅行など安易な理由では認められないと考えられています。
また、これは、改正前の相続にも適用されるので要注意です。
③ 改正法前の経過措置について
相続開始から10年経過、又は施行日(令和5年4月1日)から5年のいずれか遅い方
 相続税が発生する場合や税務上の特例を利用する時は、相続発生時から10ヶ月以内に相続人全員で相続税の申告や納税をしなければなりません。
相続税が発生する場合や税務上の特例を利用する時は、相続発生時から10ヶ月以内に相続人全員で相続税の申告や納税をしなければなりません。
ですから、原則として10カ月以内に遺産分割協議を終えることが多いです。
なお、配偶者への相続税額の軽減や小規模宅地の特例の利用の場合には、
10カ月以内に提出する相続税の申告書に、
「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、
遺産分割を延長できます。
この他には、調停・審判・訴訟などのやむを得ない事情がある場合には、
「遺産が未分割である場合についてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、
税務署長の承認を得ることにより3年という期間制限を伸ばすことができます。
3.遺産分割で負債(相続債務)の負担を決めればそのとおりになるの?
A.遺産分割協議案に同意していない債権者には対抗(主張)できません
 原則として、法定相続分に応じた負債を相続します。ご注意を。
原則として、法定相続分に応じた負債を相続します。ご注意を。
⇒遺産分割協議で負債(相続債務)の負担割合の合意をしていることがありますが、
この合意は、相続人間では有効でも、亡くなった人の債権者には対抗できません。
これは、遺産分割協議という相続人間の内輪の話だけで、
相続債権者の利益を勝手に害することはできないからです。
つまり、遺産分割でプラスの財産を相続しない者に
マイナスの財産(負債)を相続させると、
債権者は1円も回収できなくなるからです。
4.遺産が分割しにくいので、代償分割を検討したい
A.可能ですが、いくつか注意点があります。
 現実問題として、代償金の支払い能力があるのか考える
現実問題として、代償金の支払い能力があるのか考える
 税務上の問題として、遺産分割協議書の書き方や贈与税等が課税されないよう気をつける
税務上の問題として、遺産分割協議書の書き方や贈与税等が課税されないよう気をつける
 代償金の支払いを不動産などの相場があるもので行う場合は、税理士にもご相談下さい
代償金の支払いを不動産などの相場があるもので行う場合は、税理士にもご相談下さい
不動産のように分割しにくい財産が遺産のほとんどという方がいます。
そこで、代償分割という遺産の分割方法を行うことがあります。
これは、相続財産から支払えない分は、
他の現金や不動産などの権利を他の相続人に譲渡することです。
例えば、相続財産がご自宅だけという場合、
亡くなった人と同居していた長男が自宅を相続する代わり、
他の相続人(二男など)には、
不足する相続分の代わりとして現金を支給するという、
遺産分割の方法をいいます。
しかし、長男に分割で相続分を支払える収入の宛てがあるのか?
また、どのように支払い続けるのかを、よく考えて選択するべきです。
さらに、支払い能力がクリアーしても、
遺産分割協議書の書き方を誤ると、相続人間の贈与とみなされることがあります。
次のように、代償分割を現金ではなく不動産でする場合は、税務署や税理士にも相談すべきです。
代償金を他の不動産で支払うと、渡した方は譲渡所得税が、貰った方は不動産取得税が、登記の際は登録免許税などと、盛りだくさんの税金が発生します。
5.遺産が分割できないので、いっそ換価分割をしたい
A.可能ですが、いくつか注意点があります。
 現実問題として、相続登記の名義人を誰にするか、不動産会社をどこに依頼するか、いつまでに換価するかを決めるべきです
現実問題として、相続登記の名義人を誰にするか、不動産会社をどこに依頼するか、いつまでに換価するかを決めるべきです
 税務上の問題として、遺産分割協議書の書き方や贈与税が課税されないよう気をつける
税務上の問題として、遺産分割協議書の書き方や贈与税が課税されないよう気をつける
不動産のような分割しにくい財産の分割の相談が増えています。
そこで、換価分割といって、遺産を売却してその代金を分割する方法があります。
しかし、遺産分割協議書の書き方を誤ると相続人間の贈与とされるリスクがあります。
また、せっかく相続登記をしても、いつまでも売れなければ、
お金をあてにしていた相続人が困ってしまいます。
参考までに、国税庁の通達の回答の抜粋です。
共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割に関する調停の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。
※ 調停とありますが、遺産分割でも可
この他に、分割された相続分に応じて譲渡所得税がかかりますので、
その支払いのことも遺産分割の際に考えましょう。
6.相続人の一人が生きているか否か不明です。遺産分割できますか?
A.そのままでは、できません
 原則として、不在者財産管理人を家庭裁判所で選任してから遺産分割します
原則として、不在者財産管理人を家庭裁判所で選任してから遺産分割します
 失踪してから、客観的に7年を経過していたら家庭裁判所で失踪宣告を申立ても検討
失踪してから、客観的に7年を経過していたら家庭裁判所で失踪宣告を申立ても検討
遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ無効です。
・行方不明者や成年被後見人、外国に居住の法定相続人なども無視しないこと。
 令和5年4月1日より民法改正法施行(R5.5.28追記)
令和5年4月1日より民法改正法施行(R5.5.28追記)
前提:相続開始後10年経過してから利用できます。
・不明相続人の不動産持分の取得(他の共有者が取得する)
・不明相続人の不動産持分の譲渡(第三者へ不動産全体を譲渡する)
という制度ができましたが、いずれも裁判所への申立てが必要です。
この制度によって、
不明者持分を他の共有者が取得すれば、遺産分割できます。
また、不動産全体の譲渡も可能になります。
7.遺産分割協議書の不動産や預貯金の書き方がよくわかりません
A.不動産は登記簿謄本、預貯金は預金通帳の表紙(裏も)のとおりに書く。
 特定が甘い場合は、相続登記や銀行預金の解約変更のために、別途作成し直すことがあります。
特定が甘い場合は、相続登記や銀行預金の解約変更のために、別途作成し直すことがあります。
相続に関するご相談は、東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ
☎ 03-3635-2119
遺産分割で参考になるページ-墨田区 JR両国駅前の司法書士長田法務事務所
司法書士へのご相談にはご予約を

頼みやすさが付加価値の司法書士長田法務事務所
ちょっとしたご相談でも司法書士にお任せ下さい
- 長年忘れていた相続登記の相談をしたいのですが?
- 司法書士に一部の相続手続きだけを頼んでもいいの?
- 相続ではなく、不動産売買なども相談できますか?
個人の遺言・相続・不動産売却は初回無料相談があります遺言・相続・抵当権抹消・遺産整理・不動産や会社の登記など、お気軽に墨田区両国の司法書士へご相談下さい。
03-3635-2119
受付時間:10:00~18:00(平日)
セミナーや取材の受付

墨田区周辺の税理士等の士業者や不動産会社様など
こあいさつと執務案内
遺言や相続手続、高齢者向け相談、不動産の売買や贈与を中心とした墨田区両国駅前の司法書士事務所です
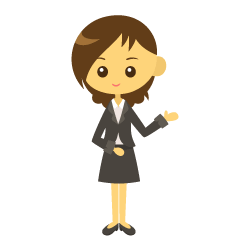
東京都墨田区の遺言相続.
netのご予約メールは24時間受付中です
営業時間:平日10~18時
※ 電話予約の時は、営業時間外予約も対応できます
03-3635-2119
メールの問合せフォーム
