遺言、相続放棄、遺産・財産管理、売買・贈与・相続・抵当権抹消等の不動産登記、司法書士による監修などのご相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所
遺言相続,不動産登記が多い司法書士長田法務事務所の公式HP
東京都墨田区両国2-21-5-507の司法書士長田法務事務所内
営業時間:平日は午前10時~午後6時、土休日は事前予約制
墨田区,江東区,台東区,江戸川区,葛飾区,荒川区,足立区,北区の相続など
司法書士の無料相談もあります
お気軽にお問い合わせ下さい
03-3635-2119
預貯金の名義変更の手続きと流れ/墨田区の司法書士長田法務事務所
墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。
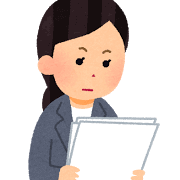
銀行等の相続による預貯金の名義変更の手続きについて
東京都墨田区の司法書士長田法務事務所では、
金融機関の預貯金の名義変更などの煩わしい手続きを、
預貯金1口座:税込4.4万円~の代行サービスを行っています。
詳しい費用は、第1の  へどうぞ
へどうぞ
☎ 03-3635-2119
相続と預貯金の名義変更へ戻る方はこちら
司法書士長田法務事務所の紹介へ
遺言・相続・贈与・抵当権抹消などの司法書士無料相談のご案内
はじめに.遺産分割前の相続預金の払戻し制度について(改正)
相続法改正により令和元年7月1日より施行
 遺産分割までに、相続預金の払い戻しができる限度額とは?
遺産分割までに、相続預金の払い戻しができる限度額とは?
限度額は、
1金融機関当り150万円(同行複数支店の合計で)です。
例えば、相続人1名あたり、
墨田銀行両国支店(100万円)と同行錦糸町支店(50万円)
の2支店の合計で150万円までがこの制度で払戻しができます。
次の2の計算式による限度額です。
 単独で払い戻しができる額とは?
単独で払い戻しができる額とは?
相続開始時の預金×3分の1×払い戻しを受ける相続人の法定相続分
例:相続預金3000万円の場合
相続人が子供2名とすると、
3000×3分の1×2分の1=500万円(相続人1名あたり)
但し、限度額がありますので、
墨田銀行では全支店で500万円のうち、
1名で150万円までの払戻しができます。
 この制度を使って払い戻すときの書類とは?
この制度を使って払い戻すときの書類とは?
1.亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡までの全部)
※ 法定相続証明情報でも可
2.相続人全員の戸籍謄本
3.払い戻し希望者の実印と印鑑証明書
※ 詳しくは、利用する金融機関の支店へお問い合わせください。
第1.預貯金の名義変更に必要な書類(一般的なもの)と費用
※ 遺産分割前の相続預金の払戻し制度を使わない、
または超えた分の解約手続きです。
通常の凍結された預貯金の払戻しを受けるための手続き
遺言書がある場合や遺産分割の有無などによって変わります。
また、銀行によって解約や変更に必要な書類は異なります。
詳しくは、通帳のある銀行の支店に直接お問い合わせ下さい。
だいたいの必要な書類や費用、司法書士報酬は、以下のとおりです。
 遺言書がある場合
遺言書がある場合
① 遺言書
② 自筆証書の場合は(家庭裁判所の)検認済み証明書つき
③ 被相続人の死亡を証する戸籍謄本
④ 遺言執行者の権限証明書(選任審判書など/遺言書に記載があれば遺言書)
⑤ 遺言執行者の実印と印鑑証明書
⑥ 受遺者の実印と印鑑証明書
⑦ 被相続人の預金通帳
 遺産分割協議書がある場合
遺産分割協議書がある場合
① 遺産分割協議書
② 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
③ 各相続人の現在の戸籍謄本
※ 法定相続証明情報があれば②③は不要です
④ 相続人全員の実印と印鑑証明書
⑤ 被相続人の預金通帳
 遺産分割協議書がない場合(法定相続)
遺産分割協議書がない場合(法定相続)
ほぼ、遺産分割協議書を除いて、②と同じ書類が必要です。
この他に、相続人代表者を相続人全員で決める書類等が増えます。
 その他に共通して書かせる書類
その他に共通して書かせる書類
金融機関ごとに指示される書類が異なります。
例えば、
必要書類一覧表を用意していて、
相続届(相続人確認書など)や委任状、
相続に関する各種依頼書(払い戻し依頼書など)などを
記入しますが、書くことが多く、相続人全員に自署させます。
銀行(金融機関)ごとに用意する書類や書式が異なることが特徴です。
詳しくは、各金融機関に直接問い合わせて見て下さい。
 預貯金の変更の費用や報酬(消費税込)について
預貯金の変更の費用や報酬(消費税込)について
だいたい、以下の費用や報酬が発生します。
 実費部分
実費部分
 金融機関が要求する費用
金融機関が要求する費用
➡ 残高証明書発行代や遺産整理受任者への送金手数料など
※ 残高証明書1通が770円から1100円が多いです
 金融機関との連絡費用
金融機関との連絡費用
➡ 支店へ行く交通費や郵送代など
※ 金融機関によっては、取引支店へ来てほしいと言われます
※ 戸籍謄本などの証明書の印紙代や交通費などの実費及び出張旅費は別となります。
 司法書士への報酬(1口座当たり)
司法書士への報酬(1口座当たり)
 預貯金の相続手続きは、1口座当たり4.4万円から
預貯金の相続手続きは、1口座当たり4.4万円から
※  預貯金等の解約だけではなく、残高証明書の発行手続きも含まれてます。
預貯金等の解約だけではなく、残高証明書の発行手続きも含まれてます。
※ 預金残高が1口座4万円以下の場合は、
その口座の報酬を半額(2.2万)に減額します。
※ 預金残高が、1口座当り1000万円を超える場合は、
1000万円ごとに1.1万円追加となります。
例:2000万円の1口座は、5.5万円となります。
なお、戸籍収集や遺産分割手続がお済でない場合は、
先に戸籍収集と遺産分割を行って下さい。
この遺産分割協議書も作成いたします。(報酬は別途必要)
※ 依頼する預金等の口座が2以下の場合について
相続登記などの預貯金以外の依頼がない場合でお客様が戸籍等を全て取得した場合には、
法定相続証明情報以外の場合は、相続人確認手数料などが別途かかります。
 お得な預貯金3定額プラン(21万7800千円・消費税込)
お得な預貯金3定額プラン(21万7800千円・消費税込)
1.条件
➡ 第1順位の日本人相続で法定相続人3名まで(例:相続人が妻と子供2名)
預金残高が1口座1000万円以下となるものが3つまで
2.含まれるもの
① 国内預貯金(証券口座除く)3口座の相続手続き
➡ 3つ迄の口座ならばお得です
② 第1順位の相続に必要な戸籍謄本の取得
➡ 印鑑証明書は含まず
③ 法定相続情報作成
➡ 税務署を含む各役所や金融機関の相続手続きで使えるアイテム
④ 遺産分割協議書作成
➡ 但し、預貯金のみ記載
※ 実費(自分で行ってもかかるもの)は別途必要です。
➡ 役所や金融機関の手数料、郵送費、交通費など
 相続登記の定額プランを申し込みの方は、
相続登記の定額プランを申し込みの方は、
オプションで預貯金ぷらす2・3があります。
ご相談ください。
相続による預貯金の名義変更手続のご依頼は、
東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ
☎ 03-3635-2119
相続と預貯金の名義変更へ戻る
相続登記定額プランへ
 証券口座(銀行の投資信託なども含む)の相続手続きは、1口座当り8.8万円から
証券口座(銀行の投資信託なども含む)の相続手続きは、1口座当り8.8万円から
※  証券口座の相続だけではなく、残高証明書の発行手続きも含まれてます。
証券口座の相続だけではなく、残高証明書の発行手続きも含まれてます。
同一人の口座でも、
金融機関の支店、口座番号、取引の種類の違いで複数口座とします。
※ 証券口座1口座に株式等の種類が8を超える場合または相続日現在の残高が3000万円以上の場合は、13.2万円からとなります。
➡ 例:1口座に、A社からJ社までの9種類の株式がある場合など
➡ 口座残高が8万円以下の口座は、割引をしますのでご相談ください。
※ 戸籍謄本などの収集費用は別途必要です。
※ 証券会社の手続きの特徴
証券会社の相続手続きは、
証券会社の社員が相続手続きに不慣れなことが多いです。
また、単純な解約と違い、遺産分割の仕方によって
相続用の口座だったり、特定口座であったりします。
さらに、証券会社の相続手続きの案内もわかりにくく、
相続書類を提出してみて、後で電話がかかってきます。
その上、新規口座開設や対象口座の移管手続きが必要なので、
相続人様の自筆で多くの質問事項に応えなければなりません。
少しでもミスがあれば、郵送でのやり取りが多くなり、
コミュニケーションが面倒です。
銀行と比べて煩雑さが違います。
さらに郵送で2~3回くらいやり取りしますので、
大変時間もかかります。
そして必ず、ご本人様又は代表相続人の方に一部を協力いただくことになります。
また、税金や相場変動の問題があるので、
慎重にならざるを得ませんし、
郵送や訪問のやり取りや問い合わせの数が銀行の数倍なのです。
※ 1口座の考え方について
預貯金や証券口座は単純に1口座と計算できないことがあります。
金融機関は、
被相続人の名前と生年月日等で名寄せしているので、
残高証明書を発行してもらうと、
一人でも、いろいろな口座番号、取引の種類がわかります。
そして、口座番号や取引の種類(例:預貯金と投資信託、
国内株式、外国株式、外貨預金などの種類)によっては、
違う書類を書かなければならず、
また、金融機関との問い合わせにも、
口座によっては、問合せ担当者が異なることがあります。
そこで、当事務所では、おおよそ、次の定義で1口座とカウントしています。
同一人名義の同一支店の口座番号1つを1口座としています。
但し、金融機関の支店や名義、口座番号が同じなら、
投資信託や株式、外貨預金もいずれも口座内8個までは、
それぞれ一口座です。
※ 例:同一人名義で同一の支店と口座番号の口座に8種類の株式=1口座
なお、1支店で複数口座がある場合、口座残高が少ない場合は、
ご相談によって割引できます。ご相談ください。
ご相談下さい。
第2.相続による預貯金の名義変更の流れ(一般的なもの)
最近は、銀行(特に都市銀行)の窓口も派遣社員が多く、
知識不足で要領が悪いことがあります。
さらに、銀行(金融機関)ごとに書式や書類を書く量やその順番が違います。
2度や3度の訪問と交渉の手間は当たり前の世界です。
 亡くなった人の金融機関の取引店へ相続の連絡します
亡くなった人の金融機関の取引店へ相続の連絡します
亡くなられた方の銀行の取引店へ訪問するか、遠方の場合は電話でお知らせします。
(都市銀行などの大手は、最寄りの支店でも対応しています)
そして、
すぐに預貯金等すべての取引が停止されて、
一切の入出金や公共料金等の引落しや口座振替等ができなくなりますので、
別の口座に変更するかを窓口で手続きの相談をして下さい。

 金融機関からの質問の後、死亡届の提出と手続に関するご案内が来ます
金融機関からの質問の後、死亡届の提出と手続に関するご案内が来ます
相続人の一人が銀行で相談後は、
死亡届書(金融機関によりタイトルが異なる)と言う書類に、
被相続人の死亡日や生年月日、
預金の種類や口座番号、
来店又は電話した方の住所・氏名・押印をします。
また、相続日の残高証明書が必要かを聞いてきます。
死亡届によって、
銀行(金融機関)は次回の手続きで必要な相続届や必要書類一覧表を用意して、
次回来店時又は郵送で書類を受け取ります。
最近は、コロナの影響からか郵送が増えています。
(但し、時間がかかります)

 金融機関から相続の種類(遺言・分割)に応じた相続届書の案内が来ます
金融機関から相続の種類(遺言・分割)に応じた相続届書の案内が来ます
今度は、前回の死亡届書等の記載事項に基づいて、
銀行から相続人代表者宛てに、
相続届書(銀行によってタイトルが異なる)と、
事例によって異なる必要書類一覧表を交付又は郵送します。
相続人全員の住所・氏名・実印の押印を求めたり、
さらに遺産分割をしているか否か、
遺言があるか否か等を記入をしてもらいます。

 必要書類を集めます
必要書類を集めます
銀行から指示された書類を市区町村役場や家庭裁判所などから取得します。

 金融機関所定の書類と必要書類を提出します
金融機関所定の書類と必要書類を提出します
相続届書を記載したら、
被相続人の全ての戸籍謄本と相続人の戸籍謄本、
(※ 法定相続証明情報でも代用できることが多くなりました)
相続人全員の印鑑証明書(3~6カ月)等を銀行に持参又は郵送します。
なお、添付した戸籍謄本等は、
事前に頼めば返却してくれことが多いです。

 金融機関が書類に不備がないと認めてから払い戻しや送金がなされます
金融機関が書類に不備がないと認めてから払い戻しや送金がなされます
不備がないことを銀行が確認したら、
2週間位で被相続人の口座を解約し、
指定相続人の口座へ送金がなされます。
第3 遺産分割の前に預貯金を引き出す時の注意
相続税がかからない相続では良くあることなのですが、
キャッシュカードの暗証番号を知っている方は、
預貯金口座が凍結される前に預貯金を引き出すことが多いです。
相続開始後の引出しは、
通帳の記帳や取引履歴からわかりますので、
葬儀代等に使用したことを記録して領収書等を保管しておかないと、
後で相続人間でトラブルになる可能性がありますのでご注意下さい。
なお、司法書士等に相談があれば、
ご相談の内容によって、
金融機関の口座解約や払戻しの手続きをします。
預金の払い戻し手続き自体は、銀行(金融機関)によって千差万別ですので、
事前に銀行(金融機関)にお問い合わせ下さい。
面倒な預貯金の名義変更は、
墨田区の司法書士長田法務事務所へお任せ下さい。
☎ 03-3635-2119
相続(全般)へ
相続と預貯金の名義変更のページへ戻る
遺産整理と相続の参考ページ
遺産整理(名義変更)と相続で知りたいことは、下の矢印の横をクリックして下さい
司法書士へのご相談にはご予約を

頼みやすさが付加価値の司法書士長田法務事務所
ちょっとしたご相談でも司法書士にお任せ下さい
- 長年忘れていた相続登記の相談をしたいのですが?
- 司法書士に一部の相続手続きだけを頼んでもいいの?
- 相続ではなく、不動産売買なども相談できますか?
個人の遺言・相続・不動産売却は初回無料相談があります遺言・相続・抵当権抹消・遺産整理・不動産や会社の登記など、お気軽に墨田区両国の司法書士へご相談下さい。
03-3635-2119
受付時間:10:00~18:00(平日)
セミナーや取材の受付

墨田区周辺の税理士等の士業者や不動産会社様など
こあいさつと執務案内
遺言や相続手続、高齢者向け相談、不動産の売買や贈与を中心とした墨田区両国駅前の司法書士事務所です
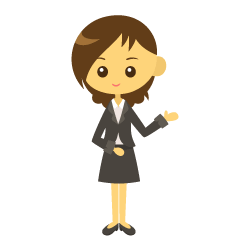
東京都墨田区の遺言相続.
netのご予約メールは24時間受付中です
営業時間:平日10~18時
※ 電話予約の時は、営業時間外予約も対応できます
03-3635-2119
メールの問合せフォーム



